行き詰まる共同親権反対論
- 宗像 充
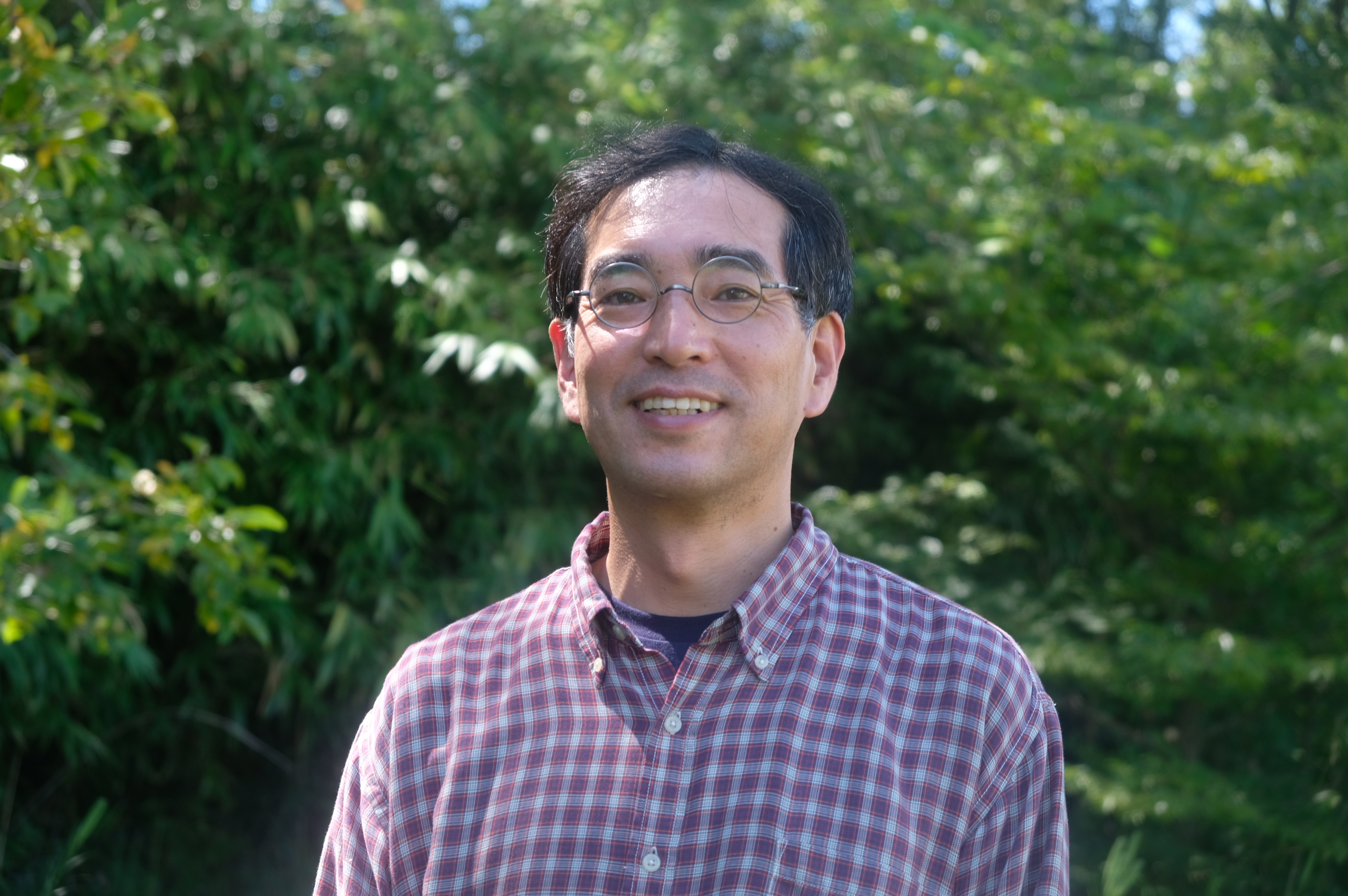
- 2024年12月19日
- 読了時間: 3分
更新日:2025年11月27日

息子さんに会えないまま亡くなった中山美穂さん
このニュースで生き別れたまま亡くなった親子に注目が集まりました。死因に事件性はなくても、これは事件ではないでしょうか。 共同親権に反対する人たちは、司法に訴えれば会えるのだから、司法手続きをとらず、とっても会えていない中山さんや、私たちのような親は「問題のある親」で、だから法改正なんて必要ないと言ってきました。
司法では2011年に面会交流が明文化された民法改正以来、原則面会交流がなされるからからというのです。
「原則共同親権実施」のウソ
なるほど、最高裁は民法に面会交流の文言が入ると、面会交流の不履行に対し間接強制の強制執行がかかる場合を判例で明示し、下級審は不履行への高額の損害賠償金を認める判例を出しました。
ところが現在、履行勧告の求めを理由も言わず拒否する家裁が相次いでいます。調停では強制執行がかかる条項の斡旋は避けられます。契約不履行なのに、面会交流の不履行についてだけ、東京高裁は損害賠償請求棄却の決定を出し続けています。
実際面会交流の調停・審判を訴えたうち、取り決められる割合はずっと5割程度で変わっていません。月に1回2時間程度の面会交流の頻度も、国会答弁で法務省の竹内民事局長がその少なさを指摘しています。下級審は最高裁を舐めてます。
男女平等に敵対する共同親権反対の人たち
子どもを奪われるという苦い経験をした私たちは、親子生き別れの慣行やそれを許す法制度はおかしいと訴えてきました。父母から生まれた子どもから見て父母の間に差はないはずです。 しかし共同親権反対の人たちは、母親が子どもを見ている現状、親権を母がとる(司法では94%)のは当然で、父親が口を出すのは家父長制の復権だと主張します。でも普通に考えてこれは母性神話です。自立を目指す女性を苦しめる理屈です。
共同親権は養育時間の父母同権を可能とするためのもの。反対しても男女平等は遠のくだけです。
人格尊重・協力義務は国の過剰介入を招く
改正民法には子どもの利益のための父母の人格尊重・協力義務が規定されました(817条12-2)。この規定は婚姻関係の有無にかかわりませんが、では「子どもの利益」は誰が判断するのでしょう。私たちの国賠訴訟の1、2審は、「婚姻外の差別的取り扱いは合理的」と、婚姻外の単独親権規定への私たちの違憲の主張を否定しているのです。
特定の子の利益を最初に考えるのは司法ではなくその子の父母です。司法の関与も、社会の基準で子の利益を損なう親の行為を国が制約するのも、父母双方に子どものためになることを考え実行する権利と責任がなければ不可能です。「親権がないからあなたは他人」なんて、中山美穂さん親子に限らず、誰が納得するでしょう。現在司法が続けている生き別れの量産は、「誰もが父母に愛されたい」と願う子どもの思いを踏みにじる非人道的な行為です。
家の内外で家族関係を峻別する婚姻外の単独親権は、日本国憲法の男女平等や個人の尊重の理念とは相いれません。単独親権制度への私たちの違憲の訴えを最高裁が受け止めなければ、今後も裁判官の性役割的な主観を排除できず、協力義務や人格尊重義務の濫用的な解釈で、多くの親子が引き離され、司法批判はやむことはないでしょう。
(2024.12.16宗像充)




コメント