判決不受理決定
- 宗像 充
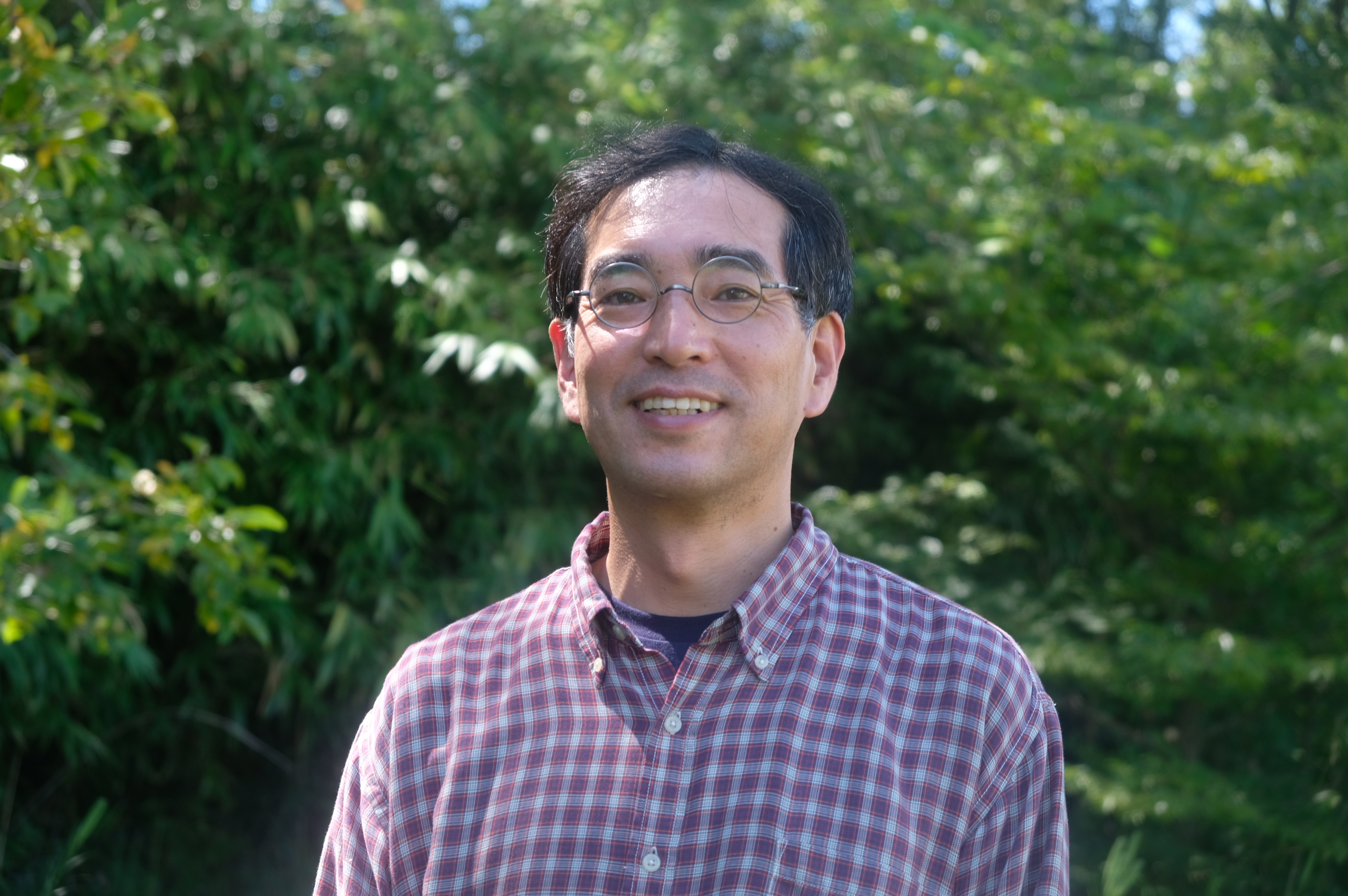
- 2025年1月28日
- 読了時間: 6分
更新日:2025年11月10日
2025年1月29日
主文 2025年1月22日の最高裁判所の判断を不受理とする。
事件の概要
最高裁判所は2025年1月22日付けで、私たちの上告を棄却・不受理の決定をしました。いわゆる「門前払い」です。この判断に対し、私たちの決定は「不受理」です。
2019年11月、12人の親たちを原告に、立法不作為による不法行為の認定と償いを求めて、私たちは国を訴える裁判を東京地裁に起こしました。法廷内外で婚姻外(離婚・未婚)においては親権をどちらかの親に定めることを強制する単独親権制度の違憲・違法性を訴えました。
この規定のもと、「先に(子を)取ったもの勝ち」の司法運用によって、多くの親たちは実質的に子育てに関与することができなくなり、親子の生き別れの被害者が日々増え続けています。子育てはすべての父母にとっての権利(憲法13条幸福追求権)であり、それを奪う法制度は憲法の平等規定(14条)に反します。その改廃を拒む国の違法性を問いました。
この制度に疑問を感じる多くの人たちが私たちの裁判に注目し、「弁論を開いて違憲判断を出せ」という最高裁門前の私たちの毎月の訴えに、大勢の仲間が集いました。
今回の最高裁の判断は、私たちの願いを踏みにじるものであり、怒り以前に司法の役割放棄の露骨さに唖然としました。今回の最高裁判断について不受理の決定をした理由は以下です。
理由
1 最高裁決定は責任回避の職務放棄
(1)責任回避
私たちが国を訴える前後から、現行の単独親権規定をはじめとする6本の親権関連の国賠訴訟が提起されています。これに対し最高裁はすべて実質審理に入ることなく門前払いの判断をしています。
昨年11月27日には、自由な面会交流を求めて立法不作為の訴訟を提起した裁判で、同じく棄却決定が出ています。私たちが第二小法廷から棄却決定を受けたのと同じ日に、自然的親子権の国賠訴訟の上告が第三小法廷で棄却されています。親子の養育関係に人権性を認めた自然的親子権の訴訟と、養育の権利性を否定した本件訴訟と高裁判断は対立しており、最高裁には統一判断を示す役割も求められていました。
何よりも最高裁は違憲判断を示すことで、組織を代表して司法運用への反省と謝罪をすべきでした。
本件の棄却判断は組織的かつ政治的なものであり責任回避そのものです。そのことはさらに同日22日、秋田市で児童養護施設から一時帰宅していた女子児童が母親に殺害されたことで行政の対応の不備を問うた損害賠償訴訟も不受理となったことから明らかです。一連の最高裁判断は非婚の親子への敵意を背景にした異論の封じ込めであり問題の先送りです。その目的は保身と組織防衛にほかなりません。
(2)「逆コース」
すでに1972年にアメリカでは、連邦最高裁が子の養育権は基本的な市民権であることに言及し、ドイツでも1982年に単独親権制度への違憲判断が出されています。この間、海外諸国からは言及するのもきりがないくらい、外交レベルの批判を日本は受け続けています。
そんな中での今回の最高裁の判断は「逆コース」そのものであり、歴史的かつ瞠目すべき職務放棄であると同時に国際社会への挑戦です。
(3)機能不全
この間、下級審は調停合意書や審判決定を守るように、あるいは、学校や行政機関が別居分離を不必要にしたことへの損害賠償の訴えを棄却し続け、最高裁も多く追認してきました。
「決まりを守らない人を叱る」のが司法の役割だと私たちは多く思いこんできました。ところが「決まりを破ったほうをほめる」ように、最高裁が下級審を促しているのです。実子誘拐という言葉が一般に知られてきた中、自力救済を促す日本の司法はもはや紛争解決機関として機能していません。
この間2024年5月には、婚姻外の共同親権を可能とする改正民法が国会で成立しました。選択的夫婦別姓や同性婚の議論がある中、国会が政治的課題の上位に位置付けたのが親権議論でした。多くの親子が会えなくなっている実態が法改正の過程で語られました。
しかし、今回の判断はこれまでの民法に何の問題もなかったという開き直りです。改正民法のもといかに多くの親子が生き別れになろうが、司法は関係ないという宣言です。
今回の私たちの訴えを否定する下級審の理屈は、現行の単独親権制度による適時適切な意思決定が子どものためになる、というものでした。しかし私たちが訴えたのは、その(目的ではなく)機能が仮にあったとしても、ではなぜ多くの親子が生き別れになる現状を受け入れなければならないのか、という誰もがすぐに思い浮かぶ疑問です。
父母の価値観が違う以上、子どものことで意見が違うのは、双方が子どものことを考えていればいるほどありふれたことです。そうである以上、「そうなったときに子どもとは引き離されても文句は言えないし、そのことで司法に来られても迷惑です」という本音と現状を、この国の人々に広く伝えるべき役割があるのは、今回の政治判断をした最高裁判所です。
(4)独善
しかし、今回の最高裁判断はそれ以前の問題です。
選挙で選ばれることのない裁判官は常に民主的な正当性を問われる立場にあります。その判断に「理由」が示され広くそれが知らされなければその判断や司法そのものが尊重されることはありません。本件訴訟は正面から子育ての権利性を問い、下級審でもその判断が揺れていました。最高裁判所は、たとえいかなる結論であったとしても、司法として判断を下すべきでした。
司法の実務に沿わない立法など司法は認めないということが今回の判断で明らかになりました。これは国権の最高機関たる立法府への挑戦であると同時に、司法の独善にほかなりません。主権者である私たちはこのような専横を受け入れる理由がありません。
2 「司法崩壊」のはじまり
昨年4月16日、笹川博義衆議院議員は国会の法務委員会で「裁判所、それから調停のあり方について、これほど不信と疑念が寄せられるとは、私自身も、想定はしておりませんでした」と吐露しています。
司法批判が表面化した中、矢面に立たされるのは、現場で利用者に対峙しながら、説得力ある言葉で何ら斡旋できない家庭裁判所をはじめとした職員たちです。最高裁の裁判官たちは、現実逃避の願望と保身のためにあえてだんまりを決め込み、現場職員を批判や怒りの矢面に立たせました。
職員を犠牲にした保身と組織防衛のために、この判決を受け入れる理由は私たちにはどこにもありません。
本件訴訟の終結をもって私たちが親子をあきらめることはありません。本訴訟で得られた成果をもって私たちは新しいスタートを切ります。と同時に今回の最高裁の判断が司法崩壊の始まりであることを、最高裁判所に言い渡します。




コメント